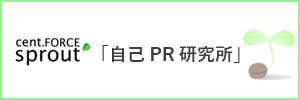■編集部注
・もしもプロジェクト YouTubeチャンネルにて、イベントの様子や防災情報をまとめた動画を公開しました。(11月 17日)
もしもプロジェクト YouTubeチャンネルにて、イベント各エリア会場やインタビューの様子を撮影した動画を公開しました。
イベントの様子はもちろんのこと、本取り組みの趣旨や参加者の声など「備え」のアップデート情報をまとめています。
【ダイジェスト編】
【体験・フードエリア編 】
【物販・展示エリア編】
【ステージ編】
【インタビュー編】
ーーーーー 以降、9月 12日公開分
8月の記事でも紹介したイベント「もしもフェス渋谷 2022」の 9月 3日(土)回に参加しました。

オープニングセレモニー前の朝 10時の時点で会場となるイベント広場には、すでにたくさんの人が訪れており、小さい子連れの家族から老夫婦、中には犬と一緒に来ている方などの姿も見えます。
オープニングセレモニーなどが行われる野外ステージでは、定期的に感染症と熱中症の注意喚起が流れていました。
テレビでよく見るマスコットキャラクター達も出演!豪華ステージイベント
■オープニングセレモニー

(左から:長谷部健さん、金山淳吾さん、髙橋忠雄さん)
11時より開始したオープニングセレモニーでは、渋谷区長 長谷部 健さん、一般財団法人渋谷区観光協会代表理事 金山 淳吾さん、こくみん共済 coop<全労済>代表理事 専務理事 髙橋忠雄さんが登壇し、テープカットを行いました。
■みんなの防災+ソナエ トークショー
最初のイベントは、局の垣根を越えて防災士、マスコットキャラクターが集う「みんなの防災+ソナエ トークショー」を開催。
こちらのイベントは午前と午後の二回開催しており、今回は午前に行われた様子を書いています。
日本テレビからはアナウンサー/防災士の岩本乃蒼さん、気象予報士/防災士の木原実さん、テレビ朝日からはアナウンサー/防災士の松尾由美子さん、TBSからはアナウンサー/防災士の伊藤隆佑さん、フジテレビからはアナウンサー/防災士の石本沙織さんが登場しました。


コールアンドレスポンスで進めていくトークショーということで、まずはじめに、来場客に「災害が発生したときにどのメディアから情報をとるか」というアンケートを取りました。
テレビ、ラジオ、ネットニュース、SNS、その他の 5択から、挙手で答えます。
テレビ、ラジオで手が多く挙がる中、一人その他を選択した方に話を聞くと「ご近所さんの口コミ」という回答が出ました。


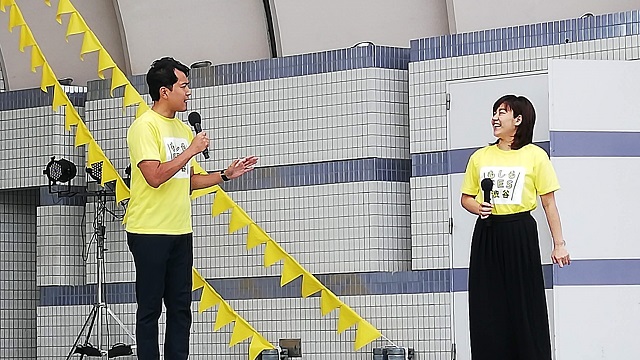
アナウンサーの方が多いということで、テレビの災害報道以外で何を行っているのかという話題に。
中継時に災害が起きた際の訓練以外にも、東日本大震災以降に入社した若手向けの生放送の対応を学ぶ勉強会を開く、地震が起きた時の呼びかけの訓練を毎日行う、カットイン(バラエティやドラマの放送中に「番組の途中ですが」から入る生放送の映像)訓練など、それぞれの局で様々な訓練を行っているようです。
NHK、テレビ東京を含む 6局のアナウンサーが集う「防災アナウンサー会議」という会議を定期的に行っている、という話もありました。

その後は観客の皆さんと一緒にお題を元にどうすれば良いのかを考えるということで、各局から防災ナビゲーターとして、そらジロー、ゴーちゃん。、ブーナ、ガチャピン・ムックが登場しました。
一つ目のシチュエーションは、『もしも「渋谷」の「昼」の「高層ビル」で、「大地震」が起こったときの「アクション」』。
頭を守る、立ってられない場合はしゃがんでしまう、頑丈な何かに捕まるなど意見が集まる中、「とにかく揺れると思うので、息子のベビーカーに覆いかぶさる」という母親の視点での意見も飛び出しました。
この場合は、階段やエレベーターなどに駆け込んだり、むやみに動かずその場にとどまる方が良いようです。
さらに「エレベーターの中で閉じ込められた場合はどうすればいいか」という追加の質問も。
非常ボタンを押して外部と連絡を取り、連絡が取れなかった場合は落ち着いて連絡が取れるのを待つのが正解。
映画のように無理に開けたり天井から出ようとしないようにと注意喚起を行いました。

二つ目のシチュエーションは、『もしも「渋谷」の「夜」の「高層ビル」で、「大地震」が起こったときの「アイテム」』。
暗い空間を照らす懐中電灯や、足元の危険を避けるの厚めの靴やスリッパなどが挙げられました。
他には帰宅困難に陥ったときに主に冬の夜など、寒い中で耐えなければいけない場合はブランケットやアルミシートなども役に立ちます。
帰宅困難の定義はおおよそ 20kmを超えたあたりで、これは歩き時間に換算すると4時間が目安となり、それ以上は難しいということで基準として設定されています。
伝言ダイヤルの番号については観客に回答を求め、これには小学生が正解の「171」を回答しました。
この番号は『大切な人がい・な・い(171)』の語呂合わせで覚えることができます。
伝言ダイヤルの制限は 30秒のため、30秒以内で何から優先して話すかを事前に考えておくのも大事とのこと。
連絡する相手と、予め何を伝えるべきか話し合うとよさそうですね。
他にも、ラジオでは避難場所や支援物資など、身近な情報を入手することができることや、危険度分布を知らせるアプリ「キキクル」の紹介など、防災の役に立つ情報が盛りだくさんのイベントでした。

■WOMEN’S WELLNESS ACTION
「WOMEN’S WELLNESS ACTION」では、一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長 長田新子さん、公益財団法人ジョイセフ 小野 美智代さん、ミュータントウェーブ(YouTuber)の山本 朝陽さん(あさひくん)、大嶋 悠生さん(おおちゃん)、大川 政美さん(まさくん)が登壇しました。

まずは「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)」についての話題から、災害時に女性の役に立つアイテムとして「デリケートゾーンをケアするシート」が挙がりました。
災害時は停電や断水などで普通の生活ができなくなり、いつも当たり前だと思っていた「お風呂」や「トイレ」も使えなくなる場合があります。
生理であることを声に出すのは勇気がいるため困っていることを伝えられず、被災者の女性たちは電気もつかない水道も通っていない家の中で、こっそり過ごさなくてはいけない状態になることも。
今まで被災時のデリケートゾーンのケアについて考えたこともなかったですが、生理周期は通常 25~38日程度と言われているので、被災したらどこかで必ずぶつかる問題と言えます。
身の回りの「当たり前になっていること」について、災害時はどうするか、今一度確認する必要性を感じました。

ミュータントウェーブの三人は元女性で現在は男性のトランスジェンダーということで、性自認が身体と異なる方ならではのお風呂に関するエピソードを語りました。
公共のお風呂では、周りの人も混乱すると思うので、男性女性と分けられると入りづらい気持ちがあるようです。
トランスジェンダーの方の中には、公共のお風呂は使わない!という選択をする人も。
また、戸籍を変更していない方の場合、証明するものがないため、トラブルの原因になりやすくなってしまいます。
他にも、病院が利用不可能でホルモン注射ができなくなり、ホルモンバランスが乱れ更年期障害の危険性や、仮設テントの割り振りの話など、他の人に比べて困ることも多いようです。

身体の健康だけでなく、心の健康を保つことも大事。
しかし被災時は気分転換にゆっくりお風呂に浸かるようなことは難しい、それでも何もしないままだと身体は凝り固まっていく、そんな時にできることといえば、という話題に。
そんなシチュエーションに推奨されているのは誰もが一度はやったことがある「ラジオ体操」なんだそうです。
毎朝ラジオ体操を行うだけでもしないのに比べて健康的になります。
安全な場所を確保してスポーツを行うのも声を出せてストレス発散にも繋がるようです。
明日は我が身、生活が今まで通りできなくなる緊急事態が起きるかもしれない。
一人一人が普段から物資の備えるだけでなく、カラダとココロを健康に保つことが大切であることを意識させられるトークショーでした。
■くまモン ステージショー

「くまモン ステージショー」では、「熊本県営業部長」兼『熊本県しあわせ部長』のくまモンが地元・熊本をアピールするのぼりを持って登場。
災害に備えて知識を蓄えるため、くまモンの動きからクイズを出題しました。

一問目、何かを袋に詰めて、各所に置くジェスチャーをしました。
問題は「非常用取り出し袋は複数の場所に置く」のは〇か×か。
正解は「〇」。
室内の他にも、玄関口や持っている人は車の中にも用意すると更に良いそうです。
二問目、走りながら板のようなものをスワイプします。スマホを操作しているようです。
問題は「非常事態の時、SNSから情報を得る」のは〇か×か。
正解は「×」。
SNSにはデマや誤った情報が大量に流れるため、ラジオなど正確な情報を得られる情報源を用意していくことが大事です。

クイズのあとは、自身の持ち歌「かモン!くまモン!」のダンスを披露しました。
のぼりを片手に軽快な動きで踊るくまモンを、観客の皆で手拍子で応援しました。
終盤、のぼりの旗が棒から抜けてしまうトラブルもありましたが、見事に踊り切り最後にポーズを決めました。
■ピットくんとジャンケン大会

「ピットくんとジャンケン大会」では、こくみん共済 Coopのマスコットキャラクター、ピットくんがピッピッとかわいい足音を鳴らしながら登場しました。
今回のジャンケン大会では、ピットくんの手が真ん丸なため、ピットくんがグーチョキパーのポーズをとり、ジャンケンを行います。
両手を腕に挙げるとパー、両手を前に突き出すとグー、そしてジャンプでチョキ。
「ピットくん、ジャンプできる?」と聞かれ、期待に応えるように大きくジャンプしました。
ジャンケン大会の景品は、防災グッズが入った「もしもフェスオリジナル防災バッグ」、見事勝ち抜いた観客の 10名へ届けられました。
■みんなの防災+ソナエ フィナーレ

9月 3日最後のステージイベント「みんなの防災+ソナエ フィナーレ」は、「みんなの防災+ソナエ」のメンバーとあいりっすん、くまモン、ピットくんがステージに揃い、観客の皆さんと一緒に写真撮影を行いました。
「もしもフェス渋谷 2022」では防災を学べる楽しい展示・体験が盛りだくさん!
「もしもフェス渋谷 2022」はステージ以外にも展示や体験など、充実したコンテンツを楽しみながら防災について理解を深めることができます。

フードエリアでは、「もしものための食体験」として、自衛隊の炊事車によるカレーの炊き出しが行われました。
提供初日は、開始 1時間前に 200名を超える行列ができ、1日 400食ほど用意したカレーがわずか 1時間で提供終了となるほどの人気ぶり。
残念ながら食べることはできませんでしたが、実際に自衛隊カレーを食べた方いわく、本格的なカレーながらも辛さを抑えられた味とのことです。
小さい子やお年寄り、刺激物に弱い方など、辛いのが苦手という方でも安心ですね。

東急ハンズ渋谷店とコラボした出張店舗「もしもストアブース」では、非常食の他、防災グッズなどの安全用品を販売。
非常食と言えば主食になるようなメニューを思い浮かべるかもしれませんが、それ以外にスナック菓子などの嗜好品も販売しており、種類の豊富さに驚きました。

SPARTAN RACEとコラボした『もしものための体力チャレンジ「SPARTAN RACE」』では、大人向け、子供向けに分かれてレースを開催。
SPARTAN RACEキッズ部門「SPARTAN KIDS」は子供たちに大人気で、中には 2回 3回とチャレンジする子供たちの姿も見られました。
一方大人向けのレースでは自衛隊員がまさかの参加する回もあり、レースの周りを埋め尽くす勢いで観客が集まるなど、どちらも白熱していました。

イベント会場内には、おぎやはぎのハピキャンとのコラボエリアも。
ここ数年のキャンプ人気で注目が集まっているキャンプグッズは防災グッズとしても活用できるということをわかりやすく紹介するハピキャンエリアでは、災害時にも役立つアイテムが多く取り揃えられ、出展社のレクチャーのもと、来場者が実際に展示物を手に取りながら体験する様子が多く見られました。
特に、車中泊体験コーナーでは、日常的に車を使うことが多い方の関心が高く、普段の備えが「もしもの備え」にもなるということを楽しみながら学んでいる様子が印象的でした。


他にも「もしも」を想定したメッセージサインや、防災の知識を学べるスタンプラリー、修理の現場などで活用される足場からの墜落防止方法の体験や、救助犬とふれあえる機会もあり、楽しく知識を学べる場となっていました。
日本では有感地震(人間の体で感じることのできる震度1以上の地震)は 1年間で 1,000回以上あると言われ、いつ大きな災害に襲われてもおかしくありません。
他にも、台風や大雨、津波など、自然災害は毎年あとを絶たない状況です。
中でも 9月は災害が多いことから「防災月間」として制定されています。
この機会にぜひ一度、防災について見直してみてはいかがでしょうか。
(情報提供:一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン、全国労働者共済生活協同組合連合会 編集・一部撮影:中嶋杏樹)